認知症で交通事故、家族の責任と損害賠償事例、弁護士費用特約の活用
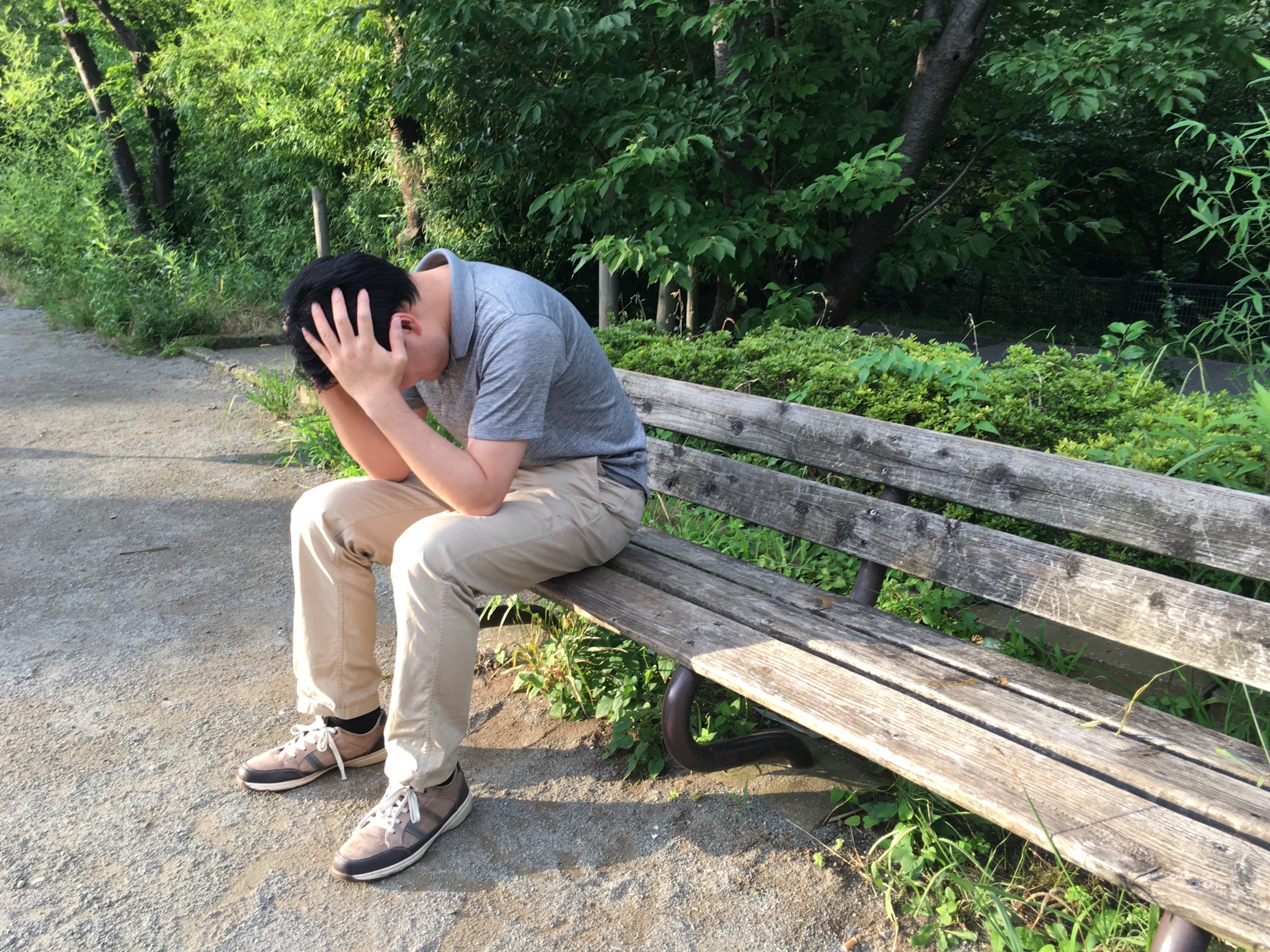
この記事はプロモーションが含まれます。
高齢化社会の進行とともに、認知症を患った家族が運転を続け、重大な交通事故を起こすケースが増えています。こうした事故では、本人の刑事責任が限定的になる一方で、民事の損害賠償責任が家族に及ぶこともあります。賠償額は数百万円から数億円に及ぶこともあり、家族にとって深刻な経済的打撃となりかねません。本記事では、家族の責任の法的根拠、実際の賠償事例の金額感、そして万一に備えるための弁護士費用特約の活用方法まで詳しく解説します。
認知症と運転事故が家族の問題になる理由
認知症では、判断力や注意力、視空間認知など運転に必要な脳の機能が低下します。症状の進行は自覚しにくく、「まだ運転できる」と本人が思い込むケースも少なくありません。家族が免許返納を勧めても拒否され、結果として事故につながる事例もあります。こうした場合、本人だけでなく、日常的に行動を監督できた家族が「監督義務を怠った」とされ、損害賠償責任を問われる可能性があります。
家族の法的責任――監督義務者責任
民法第714条は、責任能力のない者(認知症高齢者を含む)が他人に損害を与えた場合、その監督義務者が賠償責任を負うと規定しています。監督義務者とは、成年後見人や日常的に生活を共にし、行動を制限できる立場にある家族が該当します。
ただし、2016年の最高裁判例(JR東海認知症徘徊事故)では、「同居していても日常的に監督できなかった場合は免責される可能性がある」と示され、単に家族という理由だけでは責任は自動的に発生しないことが明確になりました。
交通事故の損害賠償額の現実
交通事故の賠償額は、被害の内容(人身・物損)、被害者の年齢や収入、後遺障害の程度などによって大きく変わります。以下は実際にあった、または交通事故損害賠償実務で一般的に見られる金額感の一例です。
| 事例 | 損害内容 | 賠償額(目安) |
|---|---|---|
| 認知症高齢者が横断歩道の歩行者をはね死亡させた | 死亡慰謝料+逸失利益+葬儀費用 | 3,000万〜5,000万円 |
| 認知症高齢者が店舗に突入し建物を破損 | 修繕費・営業損害 | 500万〜1,500万円 |
| 認知症高齢者が高速道路で衝突事故を起こし複数人が負傷 | 治療費・休業損害・慰謝料・車両損害 | 1,000万〜3,000万円 |
| 自損事故でガードレール・標識等を破損 | 公共物損害 | 50万〜300万円 |
賠償額は任意保険に加入していれば多くの場合保険でカバーされますが、任意保険未加入の場合や、監督義務違反で家族個人に請求が及ぶ場合は、自己負担が巨額になるリスクがあります。
任意保険加入の重要性
認知症の疑いがある場合でも、自動車保険(任意保険)の加入は必須です。対人・対物賠償は無制限に設定するのが望ましく、被害者への賠償は原則として保険から支払われます。ただし、保険会社は故意または重大な過失(免許取消後の運転など)があった場合、支払いを拒否することがあります。そのため、免許返納の手続きや運転制限の管理も重要です。
弁護士費用特約の活用方法
万一事故が起きた場合、相手との示談交渉や損害賠償請求への対応は専門知識が必要です。弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険に付帯できるオプションで、事故対応に必要な弁護士費用(着手金・報酬・実費など)を上限300万円程度まで保険会社が負担してくれます。特約を使えば、自己負担ゼロまたはごくわずかで弁護士に依頼でき、法的に適切な交渉や防御が可能です。
さらに、特約は家族全員が対象になるケースが多く、同居家族や別居の未婚の子もカバーされることがあります。加入の有無や適用範囲は契約内容を必ず確認しましょう。
家族ができる予防策とリスク回避
まとめ
認知症による運転事故は、本人だけでなく家族にも重大な法的・経済的リスクをもたらします。損害賠償額は数百万円から数億円規模になることもあり、任意保険・弁護士費用特約・免許返納など事前の備えが不可欠です。
家族としては、運転能力の低下に気づいた時点で積極的に介入し、事故防止と責任回避の両面から行動することが、最も重要な家族の責任と言えるでしょう。




