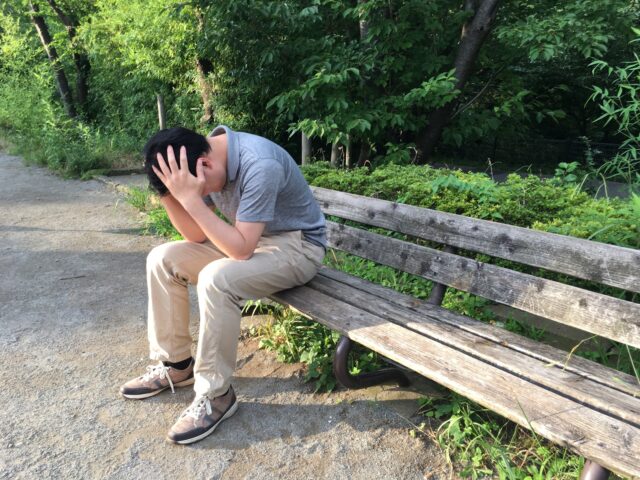認知症で運転してしまい交通事故・・・家族の責任とは?

この記事はプロモーションが含まれます。
高齢化が進む中、認知症を患った家族が運転を続けた結果、重大な交通事故が発生するケースが増えています。こうした事故では、加害者となった本人だけでなく、家族にも法的責任や損害賠償請求が及ぶことがあります。「本人の意思だから仕方がない」とは限らず、場合によっては家族が多額の賠償金を背負う可能性も否定できません。本記事では、実際の判例や法律の仕組みを踏まえながら、認知症と運転事故における家族の責任について詳しく解説します。
認知症の運転事故が問題になる背景
高齢者ドライバーによる事故の中でも、認知症が関与するケースは判断力や注意力の低下が顕著で、被害が重大化しやすい傾向があります。認知症の初期段階では本人の自覚が乏しく、家族も「まだ大丈夫」と見過ごしてしまうことがあります。しかし、現行の道路交通法では75歳以上の運転免許更新時に認知機能検査が義務付けられ、一定の基準を満たさない場合は医師の診断や免許取り消し等の措置が取られます。それでも、免許の有効期間中に症状が進行し、事故に至る事例は少なくありません。
家族が負う可能性のある法的責任
認知症の本人が事故を起こした場合、刑事責任は心神喪失・心神耗弱の程度によって問われないことがあります。しかし、民事上の損害賠償責任は別問題であり、監督義務者や使用者責任の概念を通じて家族に請求が及ぶことがあります。
民法第714条では、責任能力がない者が損害を与えた場合、その監督義務者(通常は親権者や後見人)が代わって賠償する義務を負うと定めています。認知症の場合、後見制度の有無や同居の有無、日常的な監督体制などが判断材料となります。
最高裁判例に見る家族の責任の範囲
2016年の最高裁判決(JR東海の電車事故・認知症男性死亡事件)は、家族責任の判断基準を明確にしました。この事件では、認知症の男性が徘徊中に線路に侵入し死亡、鉄道会社が家族に損害賠償を求めました。一審・二審では同居の妻と別居の長男に賠償責任を認めましたが、最高裁は長男の責任を否定し、妻についても「日常的に監督できる立場になかった」と判断して免責しました。
この判例から、単に家族だからといって無条件に責任を負うわけではなく、「現実に監督・制御できる立場にあったか」が重要視されることがわかります。
運転事故の場合に問われやすいケース
交通事故では、認知症の家族が運転を制止できる立場にあったのに放置していた場合、過失責任を問われやすくなります。例えば、明らかに運転能力が低下しているのに車の鍵を渡していた、免許返納を促さず車を自由に使わせていた、といった状況です。特に、家族が同居し日常的に行動を把握できる環境であれば、「予見可能性」と「結果回避可能性」が高いと見なされ、監督義務違反が成立する可能性があります。
免責となる可能性がある状況
一方で、家族が遠方に住んでいた、本人が強く拒否して鍵や車を隠しても運転を続けた、免許返納手続きを進めていたが事故が先に発生した、などの場合は、監督義務を果たすための現実的な手段がなかったと認められる可能性があります。最高裁判例でも「実効的な監督の可否」が免責判断の鍵になっています。
家族が取るべき予防策
事故が起きる前に家族ができることは多くあります。免許返納や運転適性検査の受診を促すこと、車の鍵やバッテリーを物理的に管理すること、地域包括支援センターや警察署の高齢者相談窓口に相談することも有効です。
また、成年後見制度や任意後見契約を活用して、法的に運転を制限できる体制を作ることも検討すべきです。これらは事故防止だけでなく、将来の法的責任を軽減するための重要な備えになります。
参考:成年後見制度とは 認知症などで判断が困難な方の契約等を補助(介護健康福祉のお役立ち通信)
参考:認知症や高齢者の「法定代理人」になれる人、成年後見人との違い(介護健康福祉のお役立ち通信)
まとめ
認知症による運転事故は、本人の責任だけでなく、家族が損害賠償請求の対象となる場合があります。しかし、最高裁判例により、家族だからといって必ず責任を負うわけではなく、監督可能性や予見可能性が重視されることが明確になりました。家族としては、免許返納や運転制限を積極的に進め、事故予防と責任回避の両面から対策を講じることが不可欠です。