高齢者が自動車を運転するときのマーク(標識)は義務?罰則は?

この記事はプロモーションが含まれます。
高齢者による自動車運転が社会問題としてたびたび取り上げられる中、「高齢者マーク」を巡る疑問や誤解も少なくありません。「あのマークは本当に義務なの?つけないと罰則があるの?」と気になったことがある方も多いでしょう。この記事では、日本の道路交通法に基づいて、高齢者マークの義務の有無や罰則、安全運転に対する配慮などをわかりやすく解説します。現役世代が感じる不安や、高齢者自身の備えとしても知っておきたい情報を網羅しています。
高齢者マークって何?どういう意味があるの?
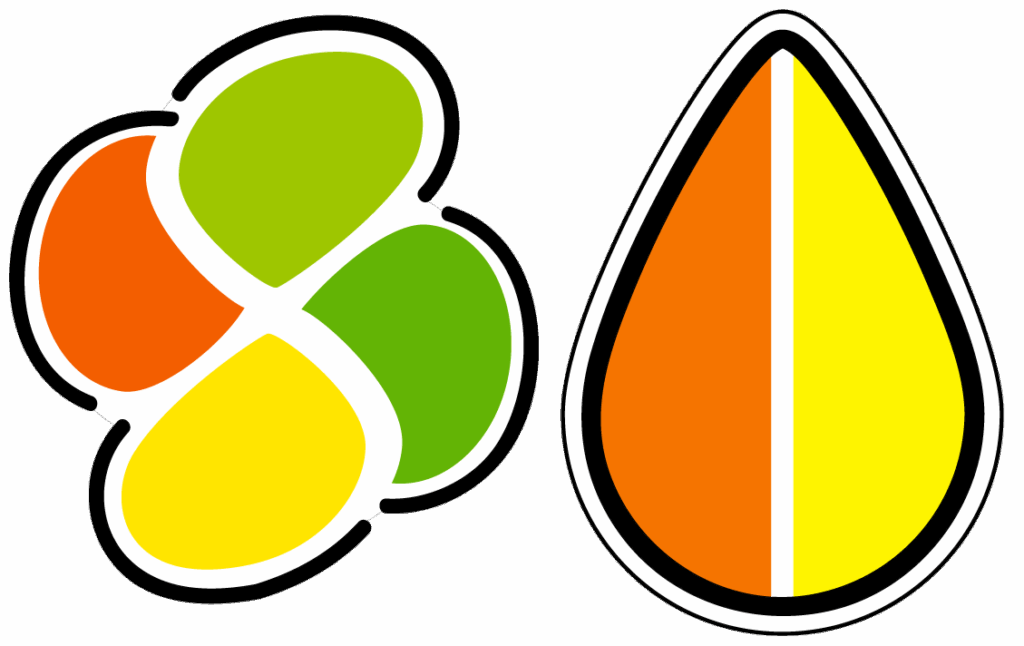
高齢者マーク(正式名称:高齢運転者標識)は、70歳以上のドライバーが自ら装着を「努力する」ことで、自分が高齢者であることを周囲に知らせるためのマークです。通称では「もみじマーク」や「四つ葉マーク」と呼ばれ、安全性を促す意思表示でもあります。高齢運転者標識は使われているデザインによって、旧タイプの紅葉型と新タイプの四つ葉型がありますが、どちらも法的には同じ効力があり使用可能です。
このマークを車体前後に貼ることで、保護義務の適用対象となり、周囲のドライバーに「配慮ある運転」が求められます。
義務なの?「努力義務」の意味とは
道路交通法第71条の5条第3項により、70歳以上の人は「加齢による身体機能の低下が運転に影響がある場合には」高齢者マークを付けるよう努めることが求められています。かつては75歳以上に装着義務がありましたが、2009年の法改正により現在は努力義務とされています。
つまり、付けないことに対する直接的な罰則は一切なく、意識的に装着するかどうかは本人の選択に委ねられているのが現状です。
高齢者マークを表示しなかったら罰せられる?罰則の有無は
論から言えば、マークを付けなかったことに対しての罰則は存在しません。努力義務であるため、道路交通法の違反とはみなされず、違反点数や罰金も科されません。
ただし重要なのは、マークを装着している車に対して周囲の車が保護義務を怠った場合、その行為(割り込みや幅寄せなど)は「初心運転者等保護義務違反」として罰則対象になる点です。具体的なペナルティとして罰金5万円以下(または反則金:普通車6,000円〜7,000円、違反点数1点)が科されます。
実際に守るべきルールは?
車に高齢者マークを貼っても運転者自身に制限が加わるわけではありません。ただし、貼られている車を追い越すこと自体は禁止ではありませんが、安全でない状況(幅寄せ・割込みなど)は道路交通法違反となります。
また高齢者マークを貼っている車は「保護されるべき存在」として扱われるため、他車の側にも周囲への配慮が法律で求められている点が特徴です。
どこで手に入る?貼る場所にもルールがある
高齢者マークは、免許更新センターや試験場、カー用品店、ホームセンター、インターネット通販や100円ショップで購入可能です。特段こだわりがなければ、ダイソーやセリア、キャンドゥなどの100円ショップでも購入できるので、そこで購入している人も多いです。いろんな場所で購入できますが価格は数百円〜1,000円程度です。
また装着場所にも注意が必要で、前後に1枚ずつ、車体高さが地上0.4m〜1.2mの範囲で貼るのが推奨されています。フロントガラスへの設置は保安基準の観点から禁止されています。
現役世代が気になるポイントまとめ
高齢者ドライバーがマークを付けた車は、法律上「配慮すべき車」に指定されており、その車への乱暴な運転(煽り・幅寄せ等)は明確に処罰対象です。現役世代の方が感じる「危険な運転」があれば、マークの有無で対応が変わることもあります。
逆に、高齢者の方へはマークを付けることで、他者から「配慮される環境」が生まれるだけでなく、自分自身の安全意識を高めるきっかけになります。「自分も周りも守るための標識」として前向きに取り入れてほしいところです。
高齢ドライバー自身が知っておくべきこと
高齢者だからといって運転をやめる必要はありませんが、体力や視力、判断力は若手と異なることを認識する必要があります。マークはその意思を伝えるツールのひとつです。
また、JAFや自治体が実施している高齢者安全運転講習、認知機能テストを利用することで、自分の運転能力を定期的にチェックしながら、より安全な運転生活を維持できます。
まとめ
高齢者マークは法律上は努力義務で、付けなくても罰則はありませんが、装着することで自他に対する意識を高め、道路上での安全性が高まります。特に現役世代が感じる高齢者の運転不安に対し、「配慮あるドライバー」という信号を送る手段でもあるわけです。ぜひ70歳を超えたら検討してみてください。

